WHOの自殺報道ガイドライン
gini氏の主張
根本的な原因は本人にしかわからない
WHOの自殺報道ガイドラインにも
「自殺の原因を単純化したり、一つの要因に決めつけたりしない」とされている
誰かのせいにしてはいけない
遺書に、恥部をさらけ出すことなど考えられないし、きれいごとを書きたいはずです
それが本当の事かもわからない
誰かのせいにしないでください
一つの原因のみ記述してないでください
最後には、本人しかわからないと結論づけてください
「他人が自殺の原因を推察すること」は思想信条の自由ですが、公にポストすることで、「報道」においてのルールが適用されると認識すべきです



自殺の原因を単純化したり、一つの要因に決めつけたりしない
自殺報道ガイドラインの「自殺の原因を単純化したり、一つの要因に決めつけたりしない」という指針は、以下のような理由と具体的な配慮に基づいています。
—
【この指針の意味】
自殺には、精神的・身体的健康の問題、家庭や人間関係の悩み、経済的困窮、社会的孤立など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。そのため、「いじめが原因だった」「失恋が原因だった」などと、一つの出来事だけに焦点を当てて報じると、誤解を与えたり、社会的偏見を助長したりするおそれがあります。
—
【具体的な説明と例】
× 悪い例(NGな報じ方)
> 「○○さんは失恋が原因で自殺したとみられます。」
このような表現は、「失恋=自殺の直接原因」と単純に結びつけており、読者に誤った印象を与えるリスクがあります。
○ 良い例(望ましい報じ方)
> 「○○さんが死亡する前、周囲には精神的な不調や悩みが見られていたとされています。複数の要因が影響した可能性があり、警察は詳しく調べています。」
このように、原因は単一ではなく複合的である可能性が高いことに配慮した書き方が推奨されます。
—
【なぜこの配慮が重要か】
1. 模倣自殺(ウェルテル効果)を防ぐため
特定の原因と自殺を強く結びつけると、似た境遇の人が「自分も同じようにすべきかも」と思ってしまう危険があります。
2. 遺族や関係者への配慮
一面的な報道は、遺族や関係者の名誉や感情を傷つけることがあります。
3. 社会的な偏見の助長を避けるため
たとえば、「うつ病になると自殺する」といったステレオタイプが広まることを防ぐためにも、慎重な言葉選びが求められます。

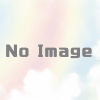
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません